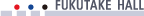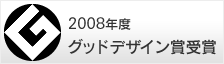- ホーム
- お知らせ
アーカイブ
2008
- 3月
- 4月
- 5月
- 6月
- 10月
- 9月
- 1月
- 6月
- 11月
- 9月
- 10月
- 11月
- 12月
- 1月
- 2月
- 4月
- 5月
- 7月
- 8月
- 9月
- 10月
- 11月
- 12月
- 1月
- 2月
- 3月
- 4月
- 5月
- 6月
- 7月
- 8月
- 9月
- 10月
- 11月
- 12月
- 1月
- 2月
- 3月
- 4月
- 5月
- 6月
- 7月
- 8月
- 9月
- 10月
- 11月
- 12月
- 1月
- 2月
- 3月
- 4月
- 5月
- 6月
- 7月
- 8月
- 9月
- 10月
- 11月
- 12月
- 1月
- 2月
- 3月
- 4月
- 5月
- 6月
- 7月
- 8月
- 9月
- 10月
- 11月
- 12月
- 1月
- 2月
- 3月
- 4月
- 5月
- 6月
- 7月
- 8月
- 9月
- 10月
- 11月
- 12月
- 1月
- 2月
- 3月
- 4月
- 5月
- 6月
- 7月
- 8月
- 9月
- 10月
- 11月
- 12月
- 1月
- 2月
- 3月
- 4月
- 5月
- 6月
- 7月
- 8月
- 9月
- 10月
- 11月
- 12月
- 1月
- 2月
- 3月
- 4月
- 5月
- 6月
- 7月
- 8月
- 9月
- 10月
- 11月
- 12月
- 1月
- 2月
- 3月
- 4月
- 5月
- 6月
- 7月
- 8月
- 9月
- 10月
- 11月
- 12月
- 1月
- 2月
- 3月
- 4月
- 5月
- 6月
- 7月
- 8月
- 9月
- 10月
- 11月
- 12月
- 1月
- 2月
- 3月
- 4月
- 5月
- 6月
- 7月
- 8月
- 10月
- 11月
- 12月
- 1月
- 2月
- 3月
- 4月
- 5月
- 6月
- 7月
- 8月
- 9月
- 10月
- 11月
- 12月
- 1月
- 2月
- 3月
- 4月
- 5月
- 6月
- 7月
- 8月
- 9月
- 10月
- 11月
- 12月
- 1月
2008
2008
2008
2008
2009
2010
2010
2010
2011
2011
2011
2011
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2024
2024
2024
2024
2024
2024
2024
2024
2024
2024
2024
2024
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2026
2015/01/08
【開催報告】ラーニングフルエイジング研究会 第4回「がん患者と家族に必要な医療とは?」
==============================================
第4回 ラーニングフルエイジング研究会
「がん患者と家族に必要な医療とは?」
==============================================
学び続け成長する存在としての高齢者、その学習にはいったいどのような課題があり、それに対して私たちはどのような方法をとりうるのでしょうか。ラーニングエイジング研究会は、ミネルヴァ書房から2015年度刊行予定の書籍『ラーニングフルエイジング:超高齢社会における学びの可能性』との連動企画です。本研究会は、高齢社会に向けた学びの可能性について様々な研究者と話し、多角的に考えていきます。
第4回の公開研究会は12月5日に福武ホールで開かれました。ゲストは東京大学医科学研究所附属病院緩和医療科の岩瀬哲さんです。「がん患者と家族に必要な医療とは?」というタイトルで、がん医療の過去と現在の実態、国の緩和ケア施策とがん拠点病院・在宅医療の問題点、地域医療連携への方策等についてお話しいただきました。岩瀬さんは東京大学医科学研究所附属病院緩和医療科で、がんの患者さんやそのご家族との相談、治療の提供、在宅ケアの準備、看取りなどに尽力されています。
1.抗がん治療と基本的・専門的緩和ケア、在宅医療との関係
古典的ながん医療のモデルにおいては、診断を行った後で治療を進めていくうちに、治療の意味がなくなってしまう時期があります。従来はこの時期以降における治療を緩和医療という風に言っていましたが、現在は厚生労働省が提供するモデルとして、診断と同時に緩和ケアと抗がん治療を行い、有機的な連携を持って治療が行われており、死後も遺族ケアが提供されています。しかし岩瀬さんはこのモデルについて、抗がん治療が死の直前まで行われるという点において現実的ではないと指摘します。実際には、がんという診断があった後に治療が行われるのは具体的には入院期間であり、死が迫ることに比例して緩和ケアが抗がん治療にとって代わり、死の直前である在宅期間には基本的・専門的緩和ケアが中心となります。さらに患者の死やホスピスへの入所を境に、専門的緩和ケアが実施されます。さらには、緩和ケアも遺族ケアにつながっているというのが岩瀬さんの考えです。
○基本的緩和ケア:患者の声を聴き共感する姿勢、信頼関係の構築のためのコミュニケーション技術(対話法)、多職種間の連携の認識と実践のもと、がんの諸症状の基本的な対処によって患者の苦痛の緩和を図ることである。
○専門的緩和ケア:専門的緩和ケアとは、基本的緩和ケアの技術や知識などに加え、多職種でチーム医療を行う適切なリーダーシップを持ち、緩和困難な症状への対処や多職種の医療者に対する養育などを実践し、地域の医療施設のコンサルテーションにも対応できることである。
(平成23年8月がん対策推進協議会緩和ケア専門員会報告書より抜粋/改変)
こうした緩和ケアは抗がん治療が終了した後に実施されますが、これらを入院から在宅まで切れ目なく行うことが現在は難しい状況です。国民の死亡場所について確認すると、1951年には自宅で亡くなる人が圧倒的ですが、1997年に病院で亡くなる人と同数となり、現在は80%近くの人が病院で亡くなっています。一方で、在宅医療に関する国民のニーズを見てみると、6割以上の人が自宅で療養したいと答えています(終末期医療に関する調査)。しかし実際は病院で過ごしてそのまま亡くなる方が多く、患者の想いと現状が乖離している状態にあるといいます。
2.「切れ目のないケア」の実施を阻む問題点
厚生労働省がん対策推進基本計画 (平成24年6月)によれば、「がん患者とその家族が可能な限り質の高い生活を送れるよう、緩和ケアが、がんと診断された時から提供されるとともに、診断、治療、在宅医療など様々な場面で切れ目なく実施される必要がある」という方針が打ち出されています。しかし実際には"切れ目なく"というところが非常に難しいです。また、在宅緩和ケアを含めた在宅医療・介護を提供していくための体制の充実をについても国の基本方針として施策が進められていますが、現場が追いついていないのが現状です。
では、具体的にはどのような問題点があるのでしょうか。岩瀬さんは、がん拠点病院を事例に次の4点を指摘します。
1つ目は、治療適応のない患者の医療環境が整うまで、入院延長は困難であるという問題です。これは、 DPC:診断群分類包括評価が孕む問題であると言い換えることができます。治療を終了した患者さんについては、治療適用がないため環境が整わないうちに退院をすすめてしまうという、追い出しが起こってしまいます。
無事に退院できたとしても、退院後に緊急事態が起こることがあります。ここで2つ目の問題は、在宅患者の緊急対応は可能でも、緩和ケアの提供は困難であるということです。がんは退院後も進行していきますが、緩和ケアチームの担当医は制度上緊急対応できないため、深夜や休日には緩和ケアを行うことができません。そもそも、がん治療は急性期病棟で行われます。
ここで、3つ目、急性期病棟で、看取り体制を敷くことは困難であるという問題が起こります。急性期病棟はもともと救急の病棟であるため、患者が死を迎えるためには過ごしづらい環境となっているのです。
そして、がん拠点病院を退院した場合、4つ目として、「緩和ケア」の提供に関する相談に対して対応が困難になるという問題が発生します。在宅医療では、がん拠点病院のように専門的緩和ケアに精通した担当者が居ないため、専門的緩和ケアが提供されないという事態が起こります。
これらと連動して、在宅医療の観点からも見た場合、次のような問題点が指摘できます。まず、緊急時の対応が困難になるという問題については、紹介元(がん拠点病院)の入院ベッドの確保の困難さが挙げられます。また、紹介元や連携病院に入院できても、「緩和ケア」は提供されないこともあります。さらに、在宅支援診療所は、紹介元の病院と「緩和ケア」の提供についての相談ができないことから、在宅で過ごす患者と家族には、いつも緊急時の不安がつきまとうことになってしまいます。こうしたことから、切れ目のない「緩和ケア」の提供は病院においても在宅医療においても難しいのが現状なのです。
3.「切れ目のない緩和ケア」の実現に向けて
では、「切れ目のない緩和ケア」を実現するためにはどうすれば良いのでしょうか。
岩瀬さんによれば、1つは、患者や家族ごとに最適な退院支援をするための中核病院を増加させることです。例えば、東京大学医科学研究所附属病院は東大病院からの転院患者が圧倒的に多く、中核病院の役割を果たしていると言えます。もう1つは、在宅―入院施設との密な連携をとることです。「切れ目のない緩和ケア」を実現するためには絶対に必要なことですが、それを実現するための体制は制度的な側面からも整っていません。
次に、東京大学医科学研究所附属病院緩和医療科の在宅連携モデルについてご紹介いただきました。抗がん治療を受けていた患者が附属病院緩和医療科に転院をした後、まずは症状をコントロールしたり、全身管理をしていきます。まだ治療を続けたいという方のためには、意思決定支援を行う一方、在宅環境調整を在宅の医療チームと連携して行うことで、退院していただきます。引き続いて症状のコントロールをしていただき、検査入院や予定入院のサイクルを回していくことで緊急入院を減らしていくという体制をとっています。こうした対処によって緊急入院はほとんど起こらなくなっています。ポイントは、多職種の連携、地域の在宅チームとの連携、退院の前には必ず合同カンファレンスを行う、そしてリアルタイムの情報共有によって緊急入院を回避することです。
東京大学医科学研究所附属病院の出したデータでは、110名の患者さんについて調査したところ、在宅の人の生存期間は長く、そうでない場合は短くなってしまうという驚きの結果が出ました。こういった結果からも、がん治療から緩和ケアになるべく早期に切り替え、緩和ケアの体制を整えることが重要だと岩瀬先生は指摘します。
がん治療においては、初期にどのような対処をするのかも重要ですが、がんの治療が終わった後はどうするのかということも考えていく必要があります。患者さんの周囲環境が一人一人違うなかで、チーム医療から地域の連携に切れ目なく移行していかなければ、不安のない生活は準備できません。そのためには、地域医療連携が必要となります。多職種が協働して事例に対応できる体制を構築することや、事例の正確な情報を共有するために、事例をフレーミングする枠組みや記述する言葉を持つこと、患者中心のコミュニケーションを実践すること、さらには患者さんの住んでいる地域のリソースを知ることが必要になってきます。
病院では、患者さん自身の容体と家族との周辺環境を考慮して、患者さんを「単純型」「複合型」「複雑型」「無秩序型」というようにフレーミングをすることがあります。多職種が協働するためには、事例の情報を漏れなく正確に共有する必要があり、フレーミングは情報を共有するための重要な手段です。多職種で正確な情報を共有し、相互理解していくために、現場ではそのフレーミング方法や工夫について話し合いが行われています。
最後に、岩瀬さんは、「がん患者と家族に必要な医療とは」という問いに対して、「切れ目のない緩和ケア」を提供すること、そして、がん患者さんや家族が中心のチーム医療を提供することが必要だと答えます。患者さんが自宅で放置されない、緊急入院という事象が起こらないということが指標となり、切れ目のない緩和ケアが目指されるべきだと述べ、講演を締めくくりました。
岩瀬さんのご講演の後、約1時間程度の質疑応答の時間が設けられました。参加者のみなさんからは、患者会や家族会と緩和医療との関わり、患者が自ら学んでいくための方策、がん治療と緩和ケアおいて実現させるべき保険制度の在り方、高齢化に伴う緩和ケアの変化など、様々な質問が投げかけられ、活発な議論が交わされました。
今回の研究会では、実際にがん患者の当事者の方もいらっしゃったことから、医療者、患者双方の視点からの質疑応答が行われたのが印象的でした。その中で、患者さんらによる緩和ケアのガイドラインの翻訳を支援したいという岩瀬さんからのご提案も有りました。患者が医療者から学ぶだけでなく、医療者と患者が協同という形で関わる機会が今後増えていくことにも期待を寄せる2時間でした。
〔ラーニングフルエイジング研究会・アシスタント:宮田舞〕