若林悠
先端科学技術研究センター 特任助教
第138回
行政学でたどる天気予報の現在
9月のUTalkは、行政学を専門とされている若林悠さん(先端科学技術研究センター 特任助教)をお迎えします。わたしたちが日頃テレビやインターネットで目にする天気予報は、実は行政活動のたまものです。気象業務が法律で定められたり、一大プロジェクトとして気象衛星が打ち上げられたり・・・行政学の観点から天気予報のこれまでをたどると、科学技術を活用して行政と民間がいかに日々の暮らしを形づくってきたのかが見えてきます。そして、大雨や土砂災害などに対する防災情報の提供に向けて、これからの気象行政はどうなっていくのか・・・?若林さんと考えてみましょう。みなさまのご参加をお待ちしております。
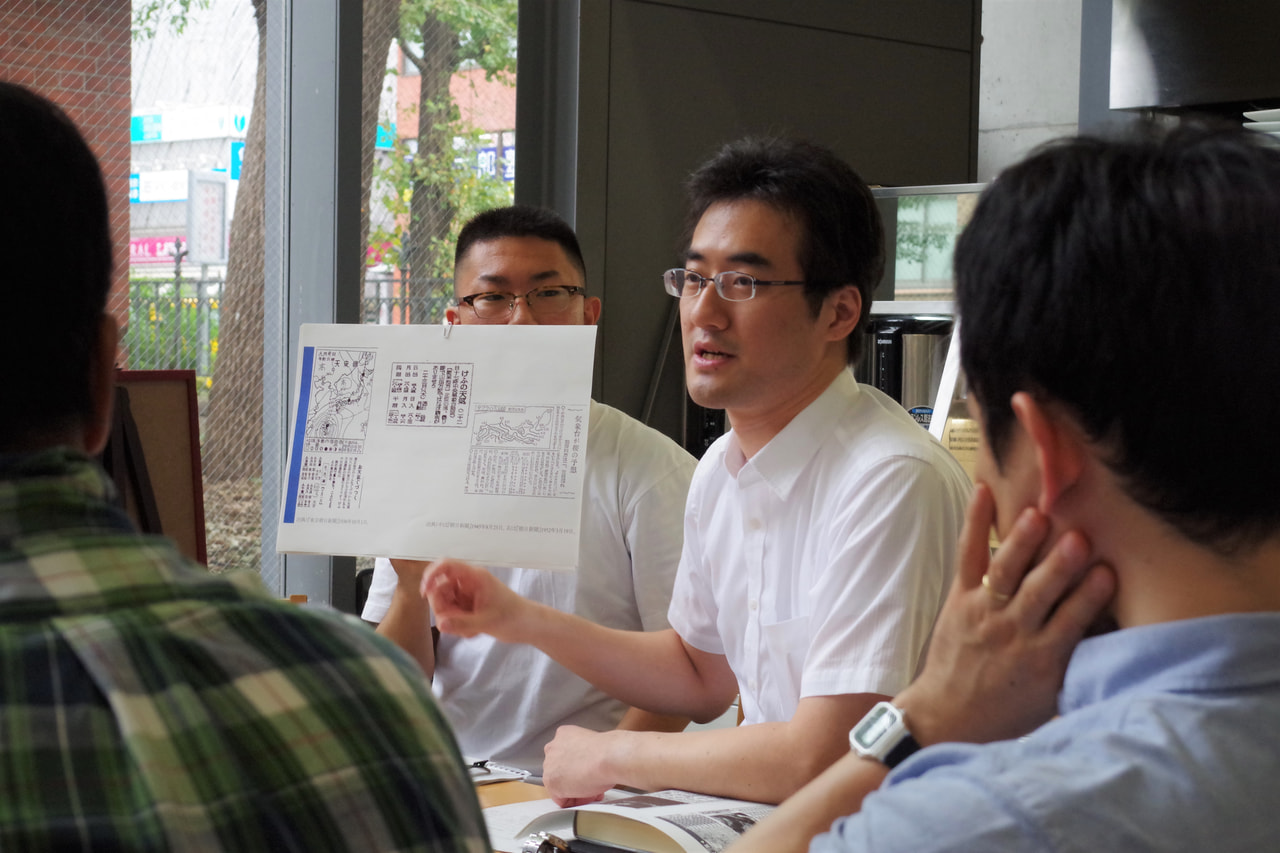

2019年9月のUTalkでは、東京大学先端科学技術研究センターで行政学を専門とされている若林悠さん(特任助教)にお越しいただきました。今回のテーマは「行政学でたどる天気予報の現在」です。
若林さんは行政学という立場から天気予報という対象を考えるにあたって、二つの視点を示すところから話をはじめました。一つ目の視点が天気予報については気象庁が「気象予報士」という資格制度を通して天気予報について規制を課しつつ、社会に広く一般にサービスもを提供しているという両面を有していること。そしてもう一つが天気予報というサービスが広い社会の需要の上で成立しているという視点です。若林さんはこの二つの視点を持ちつつ、天気予報と社会の関係を歴史的に紐解いていきました。
若林さんが提示した天気予報の最初期の事例は明治時代の新聞でした。当時の天気予報は「晴れ」や「雨」という情報が新聞の欄外に掲載される時期があものだったのですが、天気をよりわかりやすく伝えようという試みはすでになされており、天気予報にイラストを添えたり、天気に応じた俳句が掲載されたりするということもありました。現在にも馴染みがあるような天気図が大々的に新聞に掲載されるようになったのは1930年代のことです。しかし、戦争とともに貴重な軍事機密となる天気図は天気予報とともに姿を消し、再び天気図が掲載されるようになったのは戦後になってからでした。こうして再び気象サービスが提供されるようになり、「天気相談所」を設けて天気に関する相談を受け付けたほか、19504年代からは桜の開花予想を公表実施するなど、気象行政が社会に対して気象にまつわるさまざまな情報を提供する主体媒体として機能していくようになるのです。
そのなかで現在にも通じる天気予報の技術的な基盤が整っていきます。それを可能にしたのが「三種の神器」との異名を持つ「気象レーダー、アメダス、気象衛星」の存在でした。これらによる観測情報の充実化が飛躍的に進んだことによって、これまでの気象観測の職員の手による職人芸の性格の強い天気予報から、から次第にコンピューターのによる予測値にもとづくで数値天気予報を中心に据えていくが編成されていくという転換が70年代から80年代に生じることとなります。この転換を象徴したのが、降水の可能性確率をパーセンテージで表現するような確率数値予報の誕生でした。こうして1980年代において気象行政の制度は一つの到達点を迎えることになります。
しかし同時に気象庁も他の省庁と同様に行政改革の時代を迎えることになります。政府全体が小さな政府をが目指すなか、されたことによって1993年に気象業務法が改正され、天気予報の規制緩和が行われます。このときに気象予報士制度が創設され、気象庁が民間に一般向け予報気象情報を開放するとともに、資格を有した気象予報士がテレビやラジオを通して活躍するという時代が訪れるようになったのです。こうして民間事業者は従来の7日間予報よりもさらに長い10日間の予報や「洗濯指数」、「ビール指数」を発表するなど独自のサービスを展開していきました。
とはいえ、それぞれの民間事業者も気象庁の資料数値を基礎として予報しているため、よほど気象予報士の技量に差がないかぎり差別化は困難という冷静な声も聞かれるようになりました。こうして2000年代に入ると民間事業者の独自路線は下火になっていきます。他方で民間事業者が天気予報へ参入したことによって生じた官と民とのせめぎあいは、気象庁にも突きつけられた大きな課題となりました。この課問題に対して気象庁の側は防災行政をリードすることで行政機関としての社会的な信頼を得ようとします。こうして防災情報に関しては気象庁がシングルボイスを発表し、民間事業者はそれに従うという基本方針がせめぎあいのなかで確認されていく決まっていくようになるのです。
特に2010年代以降、気象庁は防災情報のを積極的な提示に努めるようになります。東日本大震災、西日本豪雨の発生を受けて2013年には特別警報がスタートし、2017年には5日先までの早期注意情報を「警報級の可能性」として発表するなど、危険なことが予想される天気予報については積極的に早い段階で告知することにより、防災官庁として存在意義を示し、組織としての生き残りを図っていくようになりました。2019年からは防災気象情報についても5段階に整理して警戒レベルを発表するようになります。こうして人々に以前より多くの情報提供を行おうとする姿勢を見せる反面、避難については「自らの判断で」避難するということが強調されるようになりました。こうした状況に対して、若林さんは情報があまりに多くなったことで逆に自己責任の側面が強く避難しにくくなり、適切な避難行動が難しくなっているのではないかという懸念を示し、気象予報士が気象情報を噛み砕いて伝えることがますます重要なのではないかと指摘します。
また、この間に気象行政がより地方のニーズに応じたサービスを提供するように変化していきました。かつての気象庁の情報提供は一方的なものでしたが、今では積極的に自治体と連携するというかたちになっています。その最たる例がJETT(気象庁防災対応支援チーム)の創設です。災害の発生が予想される場合や災害時に気象庁職員が派遣されることで現場のニーズなどに沿った的確な解説によって防災対応を支援するようなシステムが構築されています。とはいえ、あくまでも情報を提供するのが気象庁、その後の避難行動は自治体や首長が担当するという分業が取られていることからのは、気象庁が地方自治体と接近しすぎると気象情報が政治化し、バイアスがかかる危険性もあるためであり、自治体との連携については検討が重ねられている過渡期にあることを若林さんは解説していました。
参加者の方からは、政府が気象情報についてもっと避難行動等についての国民に対する指示や統制を強めるべきという意見はないのか、という質問が出ました。これに対して若林さんはむしろ民間も独自の防災情報を出したいため、気象庁による防災情報の一元化行政についての情報提供を緩和すべきだという意見のほうがしばしば聞かれるということ、そして気象庁は台風を消滅させるのではなく、警戒が主たる業務であるため、積極的に初動で動くことも重要ではあるがそれはあくまでも科学的根拠にもとづいている必要があるため、警戒情報の伝達には常に決断をめぐるぎりぎりのせめぎあいが生じているということを説明していました。
若林さんは気象庁の特色として、気象庁が政治的な組織ではないため組織存続のためには国民からの支持を得ることが重要であるということ、そして科学技術に基づいて天気予報を行っている以上、技術的なことについては慎重な姿勢を保ち、少しずつ制度変更を進めていく傾向があると組織の特性を整理されていました。
若林さん、参加者のみなさま、どうもありがとうございました。
[アシスタント:中川雄大]
