桝田祥子
先端科学技術研究センター 准教授
第137回
特許は私たちの健康を守るのか?
8月のUTalkは、知的財産法を専門とする桝田祥子さん(先端科学技術研究センター・准教授)をお迎えします。みなさんは特許にどのようなイメージを持っていますか?たとえば、新しい薬の開発には長い年月と莫大な費用を要するため、特許制度が開発者の権利と利益を守り、新しい産業を育成する役割を担っています。一方で、特許制度は安価で手に入れやすいジェネリック医薬品や、他の開発者による新しい薬の製造・販売を一定期間制限し、社会全体として見ると、私たちの健康の向上(パブリックヘルス)を阻害する要因にもなり得ると桝田さんは考えています。では、私たちの健康と特許の、より良いバランスとはどのようなものでしょうか?桝田さんのお話を通して、一緒に考えてみませんか。みなさまのご参加をお待ちしております。

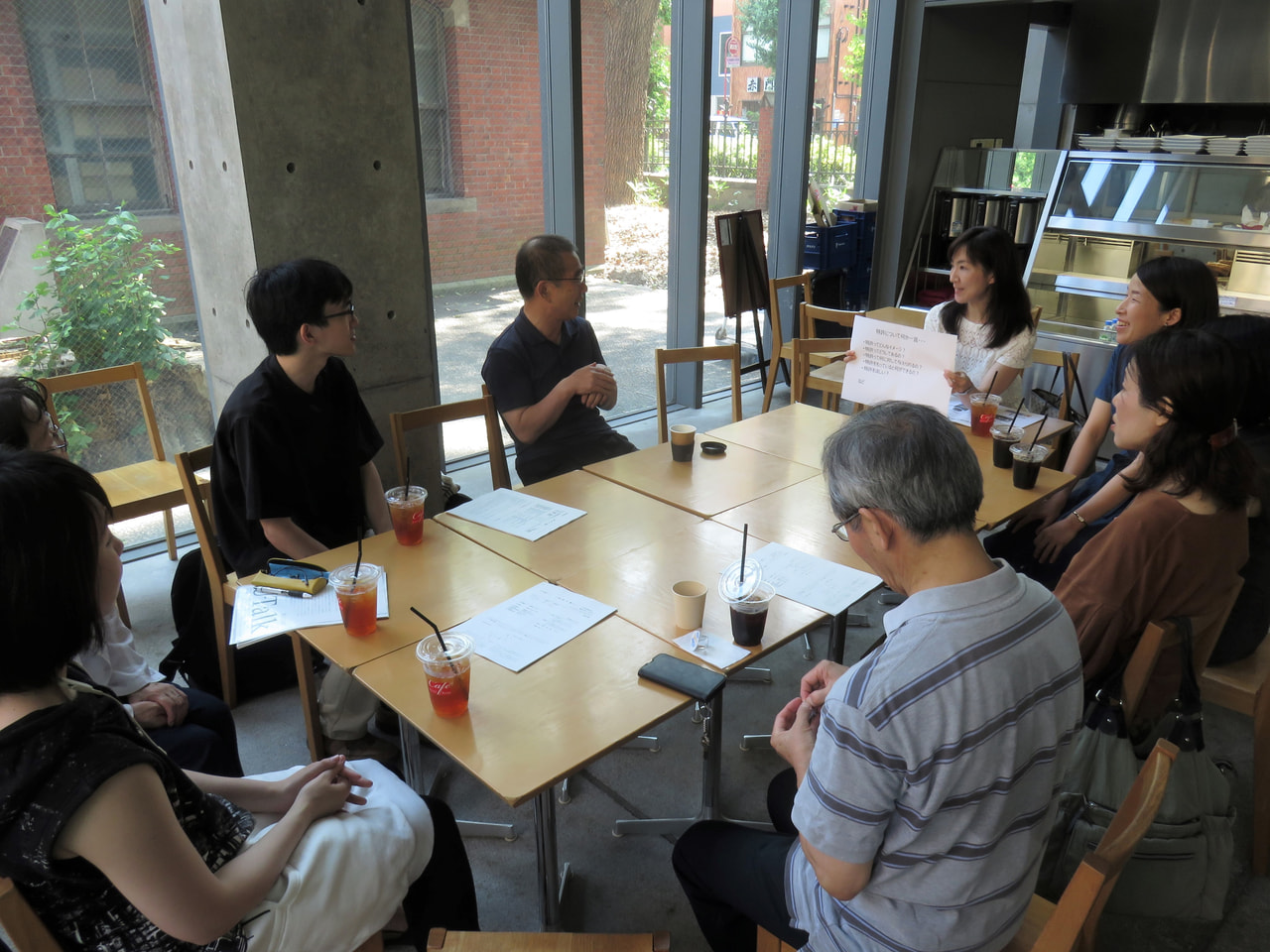
2019年8月のUTalkでは、知的財産法を専門とされている桝田祥子さん(先端科学技術研究センター 准教授)にお越しいただきました。今回のテーマは「特許は私たちの健康を守るのか?」です。
桝田さんのお話はまず特許の説明から始まりました。特許権とは、ある人が発明したアイデアを一定期間他の人や会社には使わせずに、発明者が独占的に使用することができるという権利です。特許制度の最終的な目的は産業の発達です。そのため新しい発明に対して一定期間、独占排他的権利を与えるということも大事ですが、社会におけるあらゆる発明をすべて開示するということが特許制度のもう一つの重要な点です。このことにより、他の発明者は公開されている発明を見て、さらに改良した発明を行うことが可能になります。特許がなければ、一つ一つの企業が発明を秘密にするため、既に他の人が発明したことを知らずに研究がなされることになり、無駄な研究開発投資が生じる可能性があります。特許とはこうした状況を予防することで、社会において効率的に発明活動を行うためのものであるといえます。
基本的に特許期間は出願日から20年と決まっており、ほぼ全世界で共通となっています。ただ、医薬品に関しては特種な制度があって20年よりも長くなることもあります。
桝田先生は、血中のコレステロール値を下げるために非常に多く使用されているリピトールという薬を例に、製薬のメカニズムを説明しました。この薬は1996年以降全世界で使用されて、ピーク時には年間1兆数千億円という大きな売上を上げたのですが、2010年頃から各国で特許が切れてから急激に売上は下がっています。というのも、その特許が切れた時を境目に、同じ薬効を有していながらより安価なジェネリック医薬品が市場に参加してくるからです。
ジェネリック医薬品とは、新薬の独占的販売期間が終了した後に発売される、新薬と同じ有効成分で効果・効能・用法・容量が原則同じであり、なおかつ新薬に比べて低価格な後発の医薬品のことです。当然、患者さんの多くはより安い方を使用するため、もともとリピトールが有していた市場における占有率は下がっていくわけです。
新薬創出のための投資サイクルは新しい医薬品を作るために数百億円、時に一千億円を超えるお金をかけて、10~20年にわたって研究開発を進めるというところから始まります。ここまで開発に期間が必要なのは、製薬の過程でさまざまな作業を行う必要があるからです。特に重要なのは治験の段階であり、薬効があると考えられる化合物も、そのままヒトに投与すると毒性が出ることもあるため、副作用などの安全性を確認するために動物実験をしたのち、ヒトに少しずつ投与しながら安全性を確認していきます。その後は厚生労働省に申請をし、承認されてからようやく販売へとこぎつけることができます。
この膨大な手順を踏んで新たに新薬が販売されると、通常は特許権で市場を独占できるため、そこで製薬企業は当初投じた莫大なコストを回収します。そして特許が切れると、ジェネリック医薬品の参入で売上は急激に下がっていくというメカニズムで製薬業界は動いているのです。最初に開発で使用したコストを売上で回収するためには、独占にある程度の期間を要するといえます。
このようにジェネリック医薬品は医薬品アクセスを向上させるという重要な役割をもつ反面、特許による新薬の独占期間が短いと製薬会社の大きなコストを要する新薬開発のインセンティブを奪うことになるため、両者のバランスを慎重に検討することが必要になります。
さて、日本において医薬品を対象とした特許制度が始まるのは1976年からのことです。戦後20年程度の間、日本の製薬産業はまだ成熟しておらず、日本政府としては国民に早く良い薬を安価に提供することが優先し、医薬品を特許の対象から外すという措置が取られていました。次第に日本の製薬企業が技術開発力を有するようになり、日本企業の技術力を保護することが社会的に重要であると認識され、医薬品にも特許制度が適用されるようになりました。
その後、70年代、80年代を通して、製薬企業に対する特許保護期間は延長され続けることで、製薬企業が支援されてきました。これまで、産業育成の観点から、特許保護期間が長くなる方向性で制度が設計されてきたのですが、最近は医療費抑制の観点から、ジェネリック医薬品促進政策が進んでいます。現状では特許保護期間は変わっていないものの、ジェネリック医薬品が出たら、すぐに市場に出回るような制度設計を、政府は進めています。
また戦後すぐの日本のように、国民にできるだけ良い薬を提供する必要性から、自国の製薬産業が発達していない場合には、特許の保護を弱くするという考えがはたらく傾向にあります。しかし1995年に、国際条約(TRIPs協定)が結ばれ、医薬品を特許の対象から除くことはできなくなりました。とはいえ、途上国の側からは、特許の保護については各国の状況に合わせて柔軟に運用すべきだという意見がしばしば聞かれると桝田さんは話していました。
近年、医薬品特許に関して話題になった例として、桝田さんはノーベル賞を受賞した京都大学特別教授本庶佑による「免疫チェックポイント阻害剤」の発明を挙げました。本庶教授の研究はがん細胞にPD-L1というタンパクを見つけたというものです。がん細胞は身体にとって異物です。そのため、生体の防御機構であるT細胞はがん細胞を攻撃しようとしますが、T細胞に存在するPD-1とがん細胞のPDL-1が結合することで、T細胞が攻撃しなくなるのです。本庶教授はこのメカニズムを解明し、その両者の結合を邪魔してT細胞によってがん細胞を攻撃することを可能にする薬としてオプジーボが開発されました。
このメカニズムは2003年に特許出願されたものの、あまりに先進的すぎるためその製薬開発を行うための企業を見つけることは困難でした。本庶教授は一緒に開発する企業を探すために奔走し、最初に手を挙げたのがアメリアのベンチャー企業でした。その後、最終的には小野薬品工業が製薬開発を進めて2014年にオプジーボが販売開始されるようになります。
最初から製薬企業が創薬プロセスをすべて担うこともありますが、この例のように大学からベンチャー企業や製薬企業に研究が移行し、製薬の担い手が変化していくということは多々あります。この担い手が変わる際に特許権が大事となるのです。というのも、新薬発売後の独占状態が将来的に保証されていなければ、製薬会社は多額の投資を行って研究開発するというリスクを負うことができなくなるからです。
本庶教授の研究は、もともと医薬品の開発だけを目的とするものではなく、純粋なメカニズムの発見に重きがおかれていたので、大変広い範囲の特許を取ることができました。その後、医薬品の開発に応じて特許の分割出願が行われ、多くの特許が成立しています。これが後にさまざまな問題を生じさせることになりました。
例えば、PD-1抗体医薬であるMSD社によるキイトルーダが販売された際に、小野薬品工業は、自社の保有する特許の一部に抵触するとして、MSD社に対して特許権侵害訴訟(損害賠償請求の訴訟)を起こしています。これは最終的にMSD社が小野薬品工業側に数百億円のお金を支払うことで和解が成立しています。本庶教授の研究のように、革新的な発明から得られる広範な特許は、時として他の製薬会社の製造販売に抵触することがあります。
加えて、本庶教授の例は、アカデミアの発明を事業化する際に特有の問題を示しています。アカデミアの発明が非常に利益を生むものであった際に、どこまでアカデミアの貢献が認められるべきかということを検討する必要があります。今後のがん研究支援のためにもっとアカデミアの発明の貢献を認め、利益を還元するべきだと問題提起した本庶教授意見は、大きな注目を集めました。
参加者の方のなかには特許を持っている・かつて持っていたという人もいて、活発な質疑応答がおこなわれました。参加者からは、製薬会社がまずアメリカで特許を取ろうとするのはなぜかという質問が出されました。桝田さんは、日本では治験に時間がかかりすぎるということがかつては言われていたけれど、今ではそこまで変わらず、むしろアメリカが全世界の医薬品市場の半分を占めるという経済的な理由のほうが大きいのではないかと答えていました。
桝田さん、参加者のみなさま、どうもありがとうございました。
[アシスタント:中川雄大]
